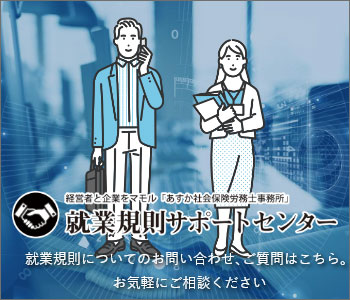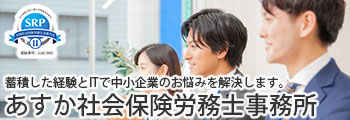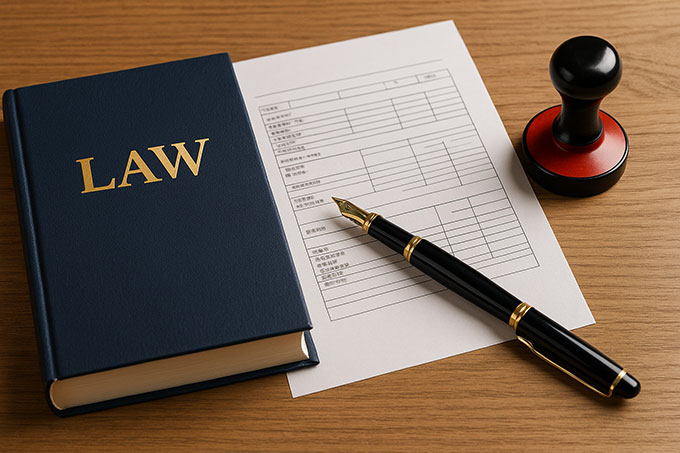
こんにちは!就業規則サポートセンターです。
突然ですが、「就業規則はうちの会社には必要ない」と思っていませんか? 法律上、社員数が10名未満の企業は、就業規則の作成・届出は義務ではありません。また、うちの会社はこれまでトラブルが起きたことはないし、特段困っていないからまだ作らなくてもいいかな、と思っている経営者もいるかもしれません。しかし、就業規則を作らないことのデメリットは意外と多く、小規模企業やスタートアップでも大きなトラブルにつながるケースがあります。
本記事では、社労士事務所に寄せられる相談をもとに、就業規則がないことで困ることベスト3をご紹介します。
第1位:トラブル発生時に「判断基準」がない
就業規則は、会社と従業員の間で共通の「ルールブック」です。 これがないと、私傷病休職や無断欠勤、遅刻、業務態度などの問題が起きた際に、どのように対応すべきか判断が曖昧になります。 例えば、同じような無断欠勤でも、人によって処分や注意の仕方が変わってしまい、「不公平だ」と不満が出ることがあります。
就業規則を作っておけば、処分や注意の基準が明確になり、公平性と一貫性を保てます。 経営者にとっても、「この対応で大丈夫だろうか」と迷う時間や精神的負担を減らすことができます。
第2位:労働条件の内容があいまいになる
給与の計算方法、残業の取り扱い、休日・有給休暇のルールなど、会社ごとに異なる取り決めは数多くあります。 就業規則があれば、これらを文書で提示して説明できますが、規則がない場合は口頭説明に頼らざるを得ません。
通常、労働条件は入社の際に労働条件通知書や雇用契約書によって説明をしますが、就業規則がないと労働条件通知書に記載内容の根拠となるものがなく、その結果、労働者によって労働条件が異なっていたり、労働条件の詳細や根拠を求められた時に明示することができず困ってしまいます。
また、口頭説明だけではニュアンスが人によって違い誤解が生じやすくなり、言った言わないというトラブルになることも往々にしてあります。 実際、「有給休暇は自由に取れる」と伝えた結果、繁忙期に複数人が同時に休みを申請して業務に支障が出た…という事例もあります。
文書化されたルールは、説明の手間を減らし、誤解やトラブルの防止につながります。
第3位:採用や社員定着にマイナスの影響
採用面接では、応募者から「休日はどれくらいありますか?」「残業はどのように管理していますか?」といった質問を受けることがあります。 就業規則があれば、その場で提示して信頼感を与えられますが、ない場合は曖昧な回答になりがちです。特に近年若い人は、年間休日日数を会社を選ぶ基準の一つにしているということを聞くこともあります。就業規則で年末年始や夏季休暇を明確にしていると、採用のときのアピールもしやすくなります。ちなみに、年末年始や夏季休暇を会社所定休日と位置付けるのか、特別休暇と位置付けるのかで、給与の時間単価が変わるので注意が必要です。
近年の求職者は働き方の透明性や制度の整備状況を重視する傾向が強く、規則がない会社は敬遠されやすいのが現実です。また、入社後にルールがあいまいだと感じると、会社に対する不信感に繋がり早期離職の原因にもなります。
まとめ:就業規則は小規模企業でも必要
就業規則は「法律上の義務」だけではなく、会社の信頼性や組織運営の安定性を高める重要なツールです。人数が少ない会社でも、ルールを文書化することで以下のメリットがあります。
- トラブル対応の基準が明確になる
- 労働条件の説明がスムーズになる
- 採用・定着率が向上する
当、就業規則サポートセンターでは、会社の規模や業種に合わせて、無理なく導入できる就業規則やルールブック作成のサポートを行っています。 「うちはまだ小さい会社だから必要ない」と思っている場合でも、一度その必要性を検討してみてはいかがでしょうか。

《この記事を書いた人》
永井正勝/社会保険労務士 歴28年
川崎市役所、独立行政法人環境再生保全機構、総務省年金記録確認神奈川地方第三者委員会の職歴を経て、平成19年に社会保険労務士登録。平成20年にあすか社会保険労務士事務所を開業。「人を大切にする企業づくりから、社会に誇れる企業」へと成長する支援に尽力する『誠意の社労士』